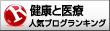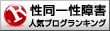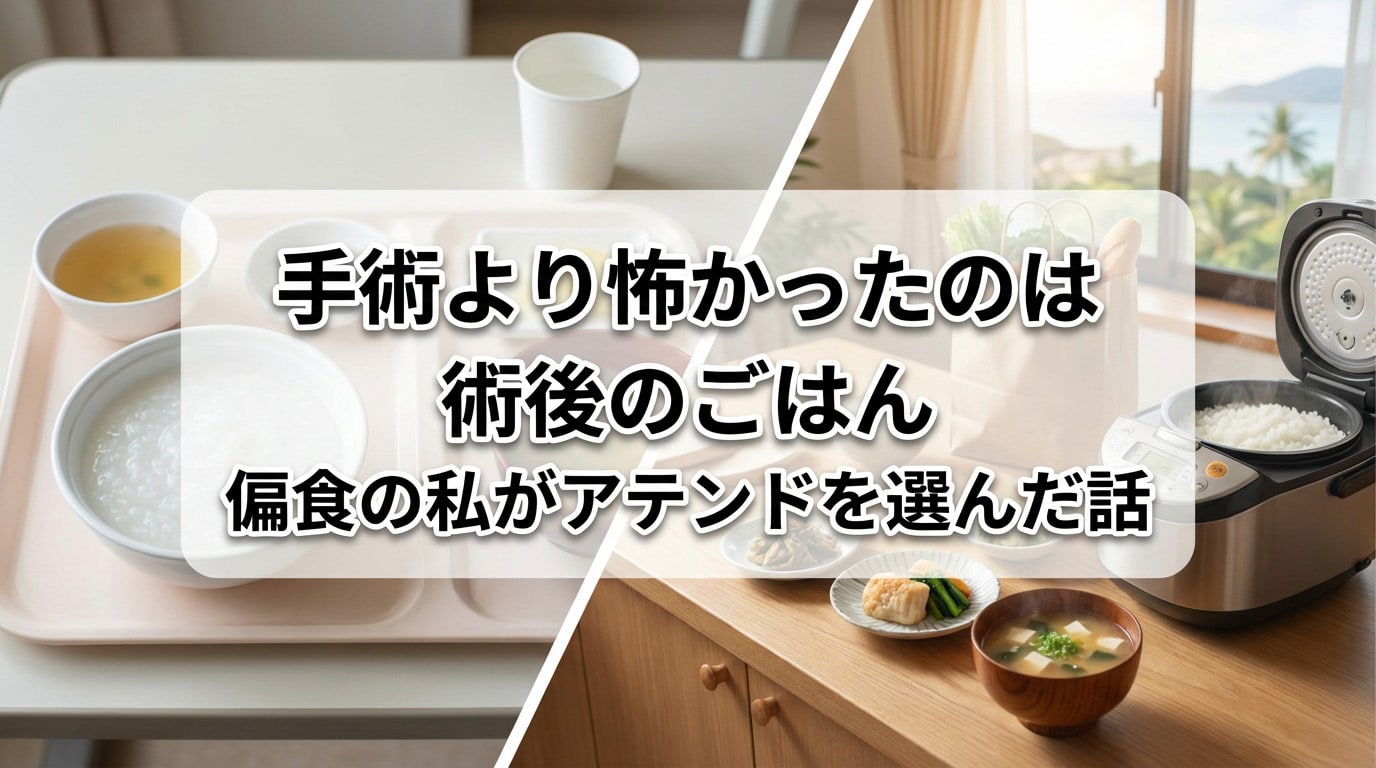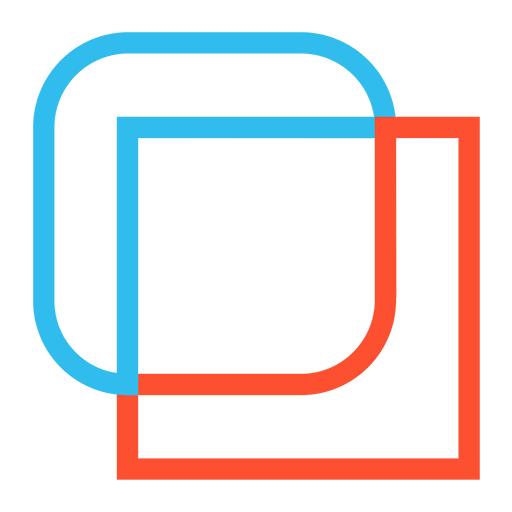双極性障害とは? ~MtFトランスジェンダー当事者の方へ~
記者:
JWC 加地
–
2025年5月3日
1,359

性別適合手術(SRS:Sex Reassignment Surgery)を予定してタイへ渡航するMtF(Male to Female)トランスジェンダーの方の中には、双極性障害と診断されているケースも少なくありません。
本記事では「双極性障害とは何か」について、基本的な症状や種類、診断方法を解説します。さらに、MtF当事者に双極性障害が併発する背景や、ホルモン治療が双極性障害に与える影響、そして手術前準備としての薬の継続服用の重要性やタイ渡航時の服薬に関する注意点についてもまとめます。
双極性障害の基礎知識(症状・種類・診断)
双極性障害とは、気分が高揚する躁(そう)状態と、気分が落ち込むうつ状態を繰り返す精神疾患の一種です。かつては「躁うつ病」とも呼ばれていました。双極性障害では、通常の気分の状態を挟んで躁状態と抑うつ状態が周期的に現れ、気分やエネルギーの振れ幅が非常に大きくなります。
躁状態になると、気分が異常に高まりエネルギッシュになります。例えば自信が極端に大きくなり、考えが次々と湧いて高速でしゃべり続けたり、睡眠が少なくても平気で活動できるなどの症状が現れます。判断力が低下し、衝動的な行動(浪費や過度の買い物、過激な性的行動など)に走ることもあります。一方、うつ状態では強い抑うつ気分や興味・喜びの喪失が見られ、疲労感に加えて不眠(または過眠)や食欲の変化が起こります。自己評価の低下や罪悪感が強まり、「消えてしまいたい」「死にたい」などといった深刻な思いにとらわれる(自殺念慮)場合もあります。
双極性障害には主に双極I型と双極II型の2つのタイプがあります。双極I型障害は、社会生活に支障をきたすほどの激しい躁状態(躁病エピソード)を少なくとも一度経験したタイプです。典型的には躁病エピソードに加えて抑うつエピソードも起こります。双極II型障害は、はっきりとした躁病エピソードがなく、代わりに軽い躁状態(軽躁エピソード)と抑うつエピソードを反復するタイプです。軽躁状態は本人が異常と感じない程度の比較的軽度な躁状態ですが、周囲から見ると普段と異なるハイテンションが察知されることがあります。双極II型だからと言って症状が軽いわけではなく、抑うつ状態が長引きやすい点が指摘されています。双極性障害の診断は精神科医が行い、DSM-5などの国際的な診断基準に基づいて、こうした躁・軽躁および抑うつエピソードの有無や程度を総合的に評価します。
MtF当事者と双極性障害:併発しやすい背景
トランスジェンダーの方々は一般人口に比べて、メンタルヘルス上の問題を併発しやすいことが知られています。社会的少数者として日常的に受ける差別や偏見によるストレス、そして身体の性と心の性の不一致による性別違和(ジェンダー・ディスフォリア)そのものが強い心理的負担となり、うつ病や不安障害など様々な心の不調が生じやすくなります。双極性障害も例外ではなく、MtF当事者でこの障害を抱えるケースは決して珍しくありません。
実際、2019年のある研究では、トランスジェンダーの患者における双極性障害の生涯有病率は約11%に上ったと報告されています。この数値は一般人口における生涯有病率(約2.6%)と比べて有意に高いものでした。なぜトランスジェンダー当事者に双極性障害が多いのか、その明確な原因については十分に解明されておらず、さらなる研究が必要とされています。少なくとも現時点では、トランスジェンダーの方々が置かれた社会的環境や少数者ゆえのストレスが、気分障害を含む精神疾患のリスクを高めている可能性が指摘されています。
ホルモン治療が双極性障害に与える影響と注意点
MtFトランスジェンダーの多くは、性別適合手術に先立って女性ホルモンの投与(エストロゲンの服用やエストロゲン注射、及び抗アンドロゲン薬の服用)によるホルモン療法を受けます。体の性別を自認する性に近づけるこのホルモン療法は、身体的変化だけでなく精神面にも良い効果をもたらすことが明らかになっています。近年のシステマティックレビューによれば、性別肯定的ホルモン療法によってトランスジェンダー当事者の抑うつ症状や心理的ストレスが有意に軽減され、生活の質が向上する傾向が示されています。ホルモン療法は主に性別違和による苦痛を和らげることで精神的な安定をもたらす治療といえます。
一方で、ホルモン療法に伴う体内ホルモン環境の変化が、双極性障害の症状やその治療に影響を与える可能性もあります。まず注意すべきは、ホルモン療法で用いる薬剤と双極性障害の治療薬との相互作用です。例えば、エストロゲン製剤は双極性障害の気分安定薬の一つであるラモトリギン(商品名:ラミクタールなど)の血中濃度を低下させ、その効果を弱めることが報告されています。実際に、エストロゲン服用中の方ではラモトリギンの必要用量が増えるケースがあり、主治医が血中濃度をモニタリングしながら投与量を調整する場合があります。ホルモン療法を開始・変更する際には、必ず事前に精神科主治医に伝え、気分安定薬や抗精神病薬などとの相互作用について確認しましょう。
また、ホルモン療法そのものが気分や感情に変化をもたらす点にも留意が必要です。ホルモンによる身体変化の過程で、一時的に情緒が不安定になったり感情の起伏(いわゆるムードスイング)が増えたりすることがあります。実際、女性ホルモン(エストロゲン)療法を受けているMtF当事者の中には、「以前より涙もろくなった」「感情の波が激しくなった」と感じる方もいます。この現象についての研究では、男性ホルモンを投与するFtMの場合は感情が平板化する一方、女性ホルモンを投与するMtFの場合は情緒の不安定さや感情表現の豊かさが増す傾向が報告されています。個人差はありますが、双極性障害の気分エピソードと区別がつきにくい感情変動が起こる可能性もあります。したがって、ホルモン療法中に気分の大きな波を感じた時は自己判断せず、すみやかに主治医に相談してください。ホルモン療法と双極性障害治療を両立させるためには、内分泌科(または産婦人科)医と精神科医の連携のもとで経過を注意深く見守ることが重要です。
性別適合手術に向けて薬を継続する重要性
性別適合手術を控えている場合でも、双極性障害の治療薬(気分安定薬や抗精神病薬など)を主治医の指示なく中断しないことが極めて重要です。手術という一大イベントの前後には、肉体的ストレスだけでなく精神的な不安や緊張も高まります。これらのストレス要因は双極性障害の症状を悪化させたり再燃させたりする引き金になりかねません。安定していた状態でも、薬を自己判断で中止してしまうと再び躁症状やうつ症状がぶり返すリスクが高まり、深刻な場合は手術の延期や中止を招く恐れすらあります。そうした事態を防ぐためにも、手術前後も含めて治療薬をきちんと継続することが大切です。
一般に、精神疾患の薬物療法は手術の前後も継続することが推奨されています。実際、気分安定薬や抗精神病薬は手術期間中も継続すべきだとする専門家の見解があります。これらの薬を中断しないことで、術後の急性期にも気分の安定を保ち、再発を予防できるからです。もっとも、手術に際しては薬剤ごとに考慮すべき点もあります。例えば代表的な気分安定薬であるリチウムは、手術中の脱水や腎機能への影響によって血中濃度が上昇し中毒を起こす危険があるため、手術の数日前から服用を中止することが推奨される場合があります。リチウムは急に止めても禁断症状の心配がない薬ですが、術後落ち着いたらできるだけ早く再開し血中濃度を管理することが望ましいとされています。このように特殊なケースもあるため、手術前の段階で主治医および執刀医(麻酔科医を含む)としっかり相談し、各薬剤の取り扱いについて指示を仰いでください。いずれにせよ自己判断で勝手に服薬を中断しないことが大前提です。主治医の指示のもとで治療を継続し、万全の精神状態で手術に臨みましょう。
タイ渡航時の服薬準備と注意点
最後に、性別適合手術のためタイに渡航する際の薬の管理について注意すべきポイントを整理します。長期の海外渡航中も双極性障害の薬物療法を中断しないことが何より重要です。そのため、自分が服用している薬が滞在期間中に不足しないよう準備すると同時に、渡航・入国時の手続きにも備える必要があります。
タイへ処方薬を持ち込む際の一般的なルールは次のとおりです:
-
持ち込み量は最大30日分まで。 個人が自己使用する目的であれば、処方薬をタイに持ち込むことは可能ですが、一度に持参できる医薬品は処方された用量で30日間を超えない範囲と定められています。滞在日数に合わせ、必要十分な量を用意しましょう。
-
英文の処方箋または医師の証明書を用意。 入国時に薬の所持を質問されたり、税関で提示を求められたりする場合に備え、英語で書かれた処方内容の説明書類を持参すると安心です。具体的には、主治医に依頼して「患者氏名・生年月日」「現在服用している薬の名前・用量・服用目的(病名)」などを記載した英文の診断書または処方箋のコピーを作成してもらいましょう。
-
薬は処方時の容器のまま持参する。 薬局から受け取った状態のシートやボトル包装に入れたまま持ち込みます。ラベル表示のないピルケース等へ小分けすると、中身が不明な薬として疑われる可能性があるため避けてください。未開封である必要はありませんが、医薬品名や用量が表示されたパッケージごと携行するようにします。
また、睡眠薬(例:ゾルピデム※マイスリーなど)や抗不安薬(例:ロラゼパム※ワイパックスなど)といった一部の向精神薬にはタイへの持ち込み制限があります。これらは乱用の恐れがある薬剤のため、所持量や手続きについて特別な規制が設けられています。その為にも、前述の「英語で書かれた処方内容の説明書類」の持参が重要ですので、必ず渡航時に持参できるように余裕を持って準備しておきましょう。
もっとも、通常の処方薬を適切な量と方法で持参する限り、入国時にトラブルとなるケースはごく稀です。実際には空港で薬について細かくチェックされることはあまりありません。ただし「万が一」に備えて必要書類を準備し、怪しまれないよう正規のパッケージで携行することが肝心です。
不明な点がある場合は、必ず渡航前までにタイSRSガイドセンター弊社スタッフまでご相談下さい。